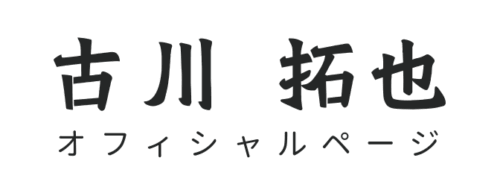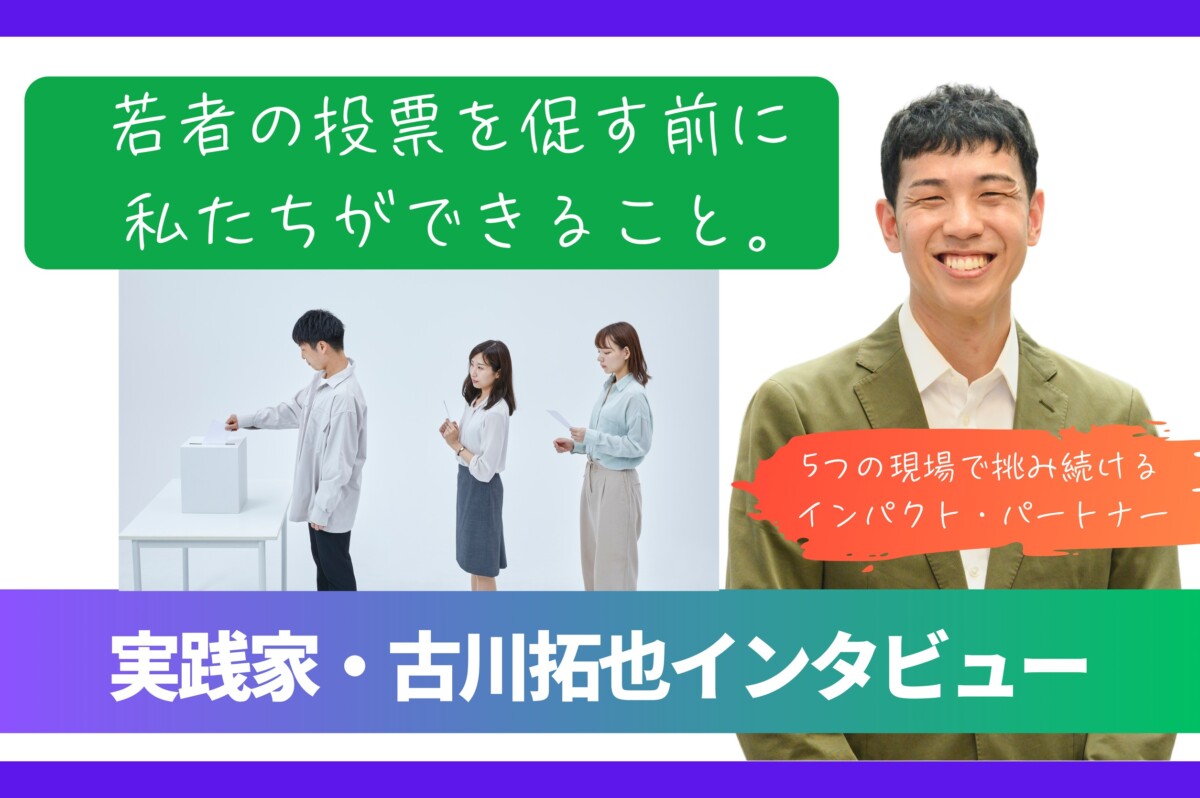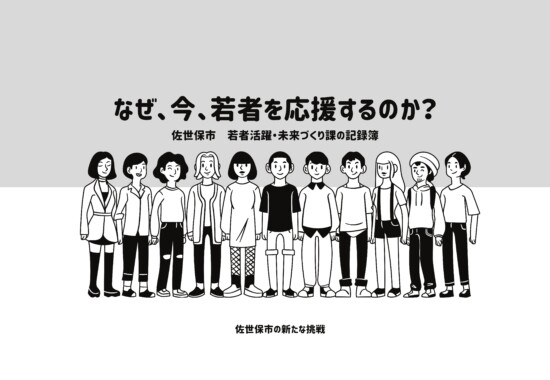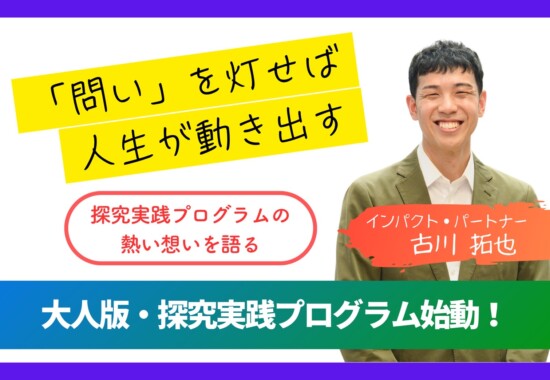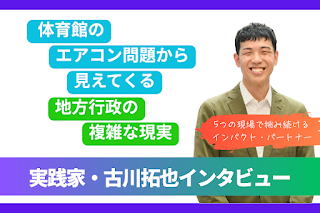若者の投票を促す前に、私たちができること。その選挙の意味と目的。―古川拓也氏インタビュー
「投票に行こう」の前に、まず「この選挙の意味」を伝えること
参議院選挙の投票日が迫る中、若者の投票率向上が再び注目されている。しかし、ただ「投票に行こう」と呼びかけるだけでは根本的な解決にはならないのではないか。
長崎の高校生の探究学習支援や佐世保の高校生による地域づくりプロジェクトSasebo Changeなど、実際に現役の高校生との関わりを持つ古川拓也氏が、若者が投票に向かう前に必要な「プロセス」について語ってくれた。
インタビュアー:川中【佐世保市在住でまちづくりや教育に関心がある同世代】
古川さんは今回の参議院選挙を前にどのような問題意識をお持ちですか。
私は基本的に若い人たち、今の10代の人たちとか若い人たちを軸に政治を見ているんですが、若い人の投票率がなかなか上がらないという問題がずっと言われていますよね。
確かに、若者の投票率の低さは長年の課題です。その原因についてはどのようにお考えですか。
個⼈的な意⾒として、まず根本的な問題があると思うんです。例えば今回の参議院選挙のような国政選挙は、どちらかというと政党を選んでいく感じになるので、税⾦の話であるとか、イデオロギー、国をどうしていくのかといった⼤きな政策が議論されていく選挙ですよね。
ところが、若い⼈たちが学校で何を教わってきたかを振り返ると、あんまり教わってないんですよ。 税⾦の仕組みがどうなってるとか、日本が抱える大きな課題とか、社会保障制度がどうなってるとか、それが理由で、選挙中に議論される物事の解像度がみんな⾼くなく、そもそも議論についていけない結果、最終的な票を入れると言う行動までの距離があるわけですね。
課題がわかりにくく抽象的すぎるということですね。
そうです。
そのため、複雑で分かりにくい課題を各政党はあえてシンプルなテーマに持っていきがちなんです。
だから国政選挙は、「⼿取りを増やします」とか、「消費税を下げます」とか、すごくわかりやすい話だったり、⽇本⼈と外国⼈の⽅の関係であるとか、そういうふうにシンプルでとっつきやすい話をメインに進んでいくので、それはそれで、なんのためにそれをやるんだろうか?とわからなくなり、すごい難しいんだろうなという、そこのつまずきがあるんだろうなと思います。
地方選挙でも同じ問題が
一方で、地方選挙についてはいかがでしょうか。
今度は地方選挙、例えば市長選挙とか県議会議員選挙になってくると、かなり身近な話になるわけですよね。そうすると今度は、そもそも自分が住んでいるまちに潜む、根深い課題って何なのか、何が大事なのかがわかりにくいという問題が出てきます。
各候補者の皆さんはマニフェストを作られるわけですが、市民の皆さんの要望がたくさんあるので、どうしても政策の数が増えていく。そうすると、さっきの国政とは逆の議論になっちゃって、 今度はミクロ過ぎて、何が争点で、どこに病巣があり、取り除く課題はなんなのか?がわからないという状況になってる。
国政選挙はテーマが大きすぎて抽象的になりやすいですが、地方選挙は課題が細かすぎて論点が見えてこないということですね。
そうなんです。そもそも何が課題の根本にあるのかも分かりにくくなるから、それはそれで「なんなんだっけ」となってしまう。
対立ではなく「より良くするための手段」として
投票に行くのも、このまま高齢者ばかりだと高齢者有利になるから若者も行けとか、あの政党には絶対に入れてはいけないとか、内容よりも対立構造を煽られている気が毎回しています。
それは確かにあると思いますね。おっしゃる通り、対立の場になってるような気がしてて。
私が思うに、本当の意味で選挙って、より良くするための手段のはずなんですよね。今があって、目の前にある課題をどう解決するのかって、その解決の仕方の違いで競うべきだと思ってるんですよ。
だから選択肢がどれがいいかという話のはずなんですけど、何か世代間の対立や考え方の対立みたいになってしまって。もちろん考え方の違いから政策の違いが出てくることはあるんですよ。あるんだけど、なんとなく、対立的で、どっちが勝つか負けるかみたいな勝負になってしまっている。
確かに、それって少しずれてる気がします。
何か少しずれてないかな、っていう。もちろんそれも大事なんですよ。だけど、もっと大切なのは、選挙をやる前が大切だと思っていて。
今の選挙は「意思表示のツール」でしかない
投票って意思表示の場じゃないですか。私はこの人に投票します、名前とか政党名書いて入れるだけじゃないですか。
そうです。意思表示を示す機会ですよね。でも、もっと前の段階で、例えば参議院選挙なら3年ごとに選挙があるわけですから、この年に選挙があるのはわかっているわけじゃないですか。任期が決まっている市長選挙とかもそうですよね。だからもっと前から政策について話し合いがされていた方がいいと思うんですよ。
その中で例えば、若い人と高齢者の皆さんが話すような機会を持ちましょうとか、若い人たちの中でこの問題はこう考えているという話し合いを持つとか、そういう場があればいいと思うんです。
アメリカの大統領選挙はすごく長いじゃないですか。選挙があるもう1年ぐらい前からずっと候補者のことを言ってるじゃないですか。だから、じっくり考える時間がありますよね。政策も含めて、ある程度理解が深まってから投票できている気がするんですよ。
確かに、日本と比べると議論の深さが違いますね。
そうです。アメリカの場合は、候補者の皆さんの思いやある意味の暗い部分もひっくるめて、だんだんそれが世の中に広まって、ある程度、6、7割ぐらいは理解できた状態で、みんな意思表示をしている気がするんですよ。
でも日本の選挙期間って2週間くらいしかなくてすごく短いじゃないですか。地方選挙で「あなたが思っている街づくりを語ってください」って私が候補者に訊いたら、なかなかすぐに答えが返ってこないと思います。市民にも「今回何が大事でしたか、この選挙で何が大事になっていたんだと思いますか」って訊いて、答えが返ってくる人もそんなにいないと思うんですよね。
だからやっぱり何が大事なのか、自分はどう判断すればいいのか。これ何の選挙なんだっていう、やっぱりそこが大切なんですよ。
学校教育での「選ぶ」体験の限界
学校教育の中で、選挙や投票について学ぶ機会はありますが、どのような課題があるとお考えですか。
学校では生徒会長の選挙とかがありますよね。でも、あれって学校が必ずこの日だって決めて、半ば強制的に投票させるわけじゃないですか。
多分、小学校や中学校では体育大会の団長を決めるとか、生徒会長を決めるとか、そういう「誰かを選ぶ」という行為で終わってしまっていると思うんですよ。学校現場はあまり政治的なことを言っちゃいけないという決まりがあるので、言えないのは理解できるんですけど。
選ぶ行為の練習だけで終わってしまっているということですね。
そうです。どう選べばいいのかとか、何を基準にすればいいのかが全然わからないままに、いきなり18歳で「投票してくださいね」と言われても、「何?」ってなるじゃないですか。
投票を促す前に必要な「説明」
では、若者の投票参加を促すために、どのような取り組みが必要だとお考えですか。
例えば20代ぐらいまでの人たち向けに、投票する人の選び方みたいなことをやってもいいと思うんです。いきなり「投票に行こう」って言われても困るじゃないですか。
その前にもうちょっと、この選挙はこういう意味があって、例えば市議会議員選挙ってどういう意味があって、あなたが入れる1票がどういう目的のための1票ですよ、ということをちゃんと説明した方がいいと思うんです。
具体的にはどのような説明が必要でしょうか
何の政策が良いとか悪いとか言う前に、そもそも市議会議員の皆さんがなぜいるのかとか、そこからまず始めた方がいいと思うんですよ。
例えば、市議会議員や県議会議員の皆さんは、執行部と呼ばれる県庁とか市役所の人たちがやっていることをチェックして、予算を決めていくという役割なんですね。市民の皆さんの意見を反映させることもそうだし、きちんと仕事をしているかを監督するという役割もある。
チェックし、監督する人を選ぶ選挙だという認識が重要ですね。
そうです。誰にその監督してもらうのかという選択ですよね。県庁の人も市役所の人も、基本的には自分のまちが良くなって欲しいと思って働かれているので、よっぽどのことがない限り変なことにはならないと思うんです。ただ、やっぱり第三者的な視点で「これどうなの?」とか、実際に市民に近いところから見るとこうだよね、みたいな役割は必要で。
その目線で見たときに一体誰がいいんだろうか、という判断をする。そういう「まちの仕事を監督する人を選ぶ選挙だよ」って言うと、全然違うと思うんですよ。
市長選挙は「まちのデザイナー」を選ぶこと
市長選挙についてはいかがでしょうか。
市長を選ぶっていうのは、これはものすごく重要で、住民にとって市とか町のトップを選ぶっていうのは、そのまちの予算もそうだけど、人事とか、議会を解散するということもできるわけで、小さな国の大統領みたいな感じですよね。
すごく重要なわけですよ。権限がそこに集中しているので、どういう”まち”にするかっていう、言ってしまえば、デザイナーなわけです。市長選挙はその”まち”をどうデザインするかを決める選挙ですよ。
”まち”のデザイナーを選ぶという視点は分かりやすいですね。
どういう”まち”にしたいのかというところで選んでいくわけじゃないですか。だから、そういう目的を私はちゃんと知りたかったなと思って、10代とか20代のときに。
身近な政策から学ぶ重要性
若いうちに行政の取り組みを知る機会として、具体的にはどのようなことがあるでしょうか。
例えば地域の活動をしていると、どうしてもそのまちの政策にぶつかるわけですよね。
例えば、ゴミ拾い活動をひとつ見てもそうですよ。市民大清掃みたいなのをやりますってするじゃないですか。あれはゴミ拾いでまちを綺麗にしようって話ですが、そもそもそのゴミ処理の費用はどうなっているのかっていう話で、これって、市民でみんなで綺麗にするということで、多分ボランティアでやるからその費用は特に取らずに市の方で処分しますよっていうふうになっているんだと思うんですよ。
でも、この決定って、当然行政がしているわけです。これも小さな政策なわけですよ。街を綺麗にするという意識を広めるために、普通だったらゴミ袋代がかかるでしょう。でもそれを無料にしているってことは、市がお金を出しているってことですよね。
給食の無償化だってそうですよね。給食は無料なんだよって言われても、でもなんで無料なのかっていう話。ここをちゃんと説明してあげていいと思うんですよ。なぜ敬老パスがあるのかとかも含めて、説明してあげてもいいはずなんです。
行政の取り組みとして、勝手にそうなっているのではなく、誰かが決めているものである、ということはちゃんと伝えてあげてもいいのかなっていう気はしますね。
投票はゴールではなくスタート
教育的な視点で見ると、選挙後の振り返りについてはいかがでしょうか。
振り返りってあまりしないですよね。例えば現職の方が出られているとするじゃないですか。「私はこれができました」って言うんだけど、何と照らしてできたのか?が大切ですよね。その前の選挙のときに約束していたものがどうなっているのか、そこを確認すべきですよね。
学校では「振り返りをして何ができなかったか反省して、また次のステップに行こうね」って言うんですけど、政治の世界ではどうでしょうか?と思うことが多々あります。
良いことも悪いことも含めて、こう選挙の時は言ったけど、実はやってみたら「やっぱり無理でした」で、別にいいと思うんですよ。今の10代の子とか20代の子たちって、できなかったっていうのは、できなかったらそれはそれでしょうがないよね、って切り替えられるんですよね。
わりとドライに切り替えるんですよ。できなかったことですごくネガティブに落ち込むんじゃなくて、もうしょうがないしょうがないっていう。我々が思っているより全然理解できるんですよ。だけど、それをあいまいにされるのがすごく嫌なんだろうなと思います。
だから、うやむやにされるより、できなかったことを素直に伝える方が誠実に映る。結局何も変わらないじゃないかと落胆させる前に、こういうふうに変えようとしたけれど、ここに問題や課題があって今回はできなかった、そういう姿をきちんと若い人たちにも見せて伝える、それが次世代の政治に求められることの一つなのではないか?と思います。
今の若者世代への期待
今の若い世代については、どのような可能性を感じていますか。
今の若い皆さん、10代の方々は、総合的な探究の時間とか、SDGsとか地域課題解決を考えることに慣れており、我々の時代の時よりもソーシャル的な物に対して、想像がつきやすいと思います。
SDGs的な、要するに世の中全体が良くならないと駄目だよね、誰かがよければそれでいいみたいな世界じゃないよね、みたいなのは、感覚的に実は持っているので。
きちんと説明すれば理解してもらえるということですね。
そうです。きちんと話せば、私は分かると思うんですよ。だから、「投票に行こう」じゃなくて、もうちょっと「今回はこういう人たちが選べます、こういう選挙なんですよ」っていうプロセスを説明できないのかなと思うんです。
「第何回参議院選挙です、みんなで投票行こう」じゃなくて、「そもそも参議院はどういう役割の人で、何の目的でどれを選ばなきゃいけないのか」みたいなところから始めた方がいいと思うんです。
そこぐらいだったら、教育の現場で話しても全然問題ないと思うんですよ。その辺りをもうちょっと頑張った方がいいんじゃないかなという気はしますね。
すなわち、制度を変える前にできることがもうちょっとあるから、皆さんと力を合わせて何か変えられるといいなと思います。やれそうなところはどんどんやっていきたいですよね。
若者の投票参加を促すためには、まず「この選挙がどういう意味を持つのか」というプロセスを丁寧に説明することが重要だということですね。
そうした場をどんどん作っていきたいと私もお話を聞いて思いました。本日は貴重なお話をありがとうございました。
おわりに
古川さんのインタビューを通じて見えてきたのは、若者の投票率向上の鍵は「投票に行こう」という呼びかけの前にあるということだ。
今の若者たちは決して政治に無関心なわけではない。むしろ、SDGsや地域課題解決といった活動を通じて、社会を良くしたいという意識は十分に持っている。必要なのは、その意識と選挙という仕組みを結びつける説明なのだ。
国政選挙はテーマが大きく抽象的で理解しにくく、地方選挙は住民のニーズが細かすぎて論点が見えにくい。この状況を変えるためには、教育現場や地域社会が協力して、選挙の意味や役割を日常的な体験と結びつけて説明していく必要があるだろう。
古川さんが語った「選挙後の振り返り」も重要である。今の若者は「できなかったことはしょうがない」と理解できる一方で、「あいまいにされること」を嫌う。この特性を理解し、透明性のある政治プロセスを作り上げることが、真の意味での若者の政治参加につながるのではないだろうか。
「投票に行こう」の前に、まず「この選挙の意味」を語る。そのシンプルな発想の転換が、日本の民主主義をより豊かなものにしていくはずだ。
———古川拓也からのお知らせ———
現在、古川拓也の取り組みに共感し、応援をしたい!というサポーター・寄付を募集しております。ぜひ、ご検討のほどよろしくお願いいたします。寄付ページは以下のバナーをクリックしてご覧ください。