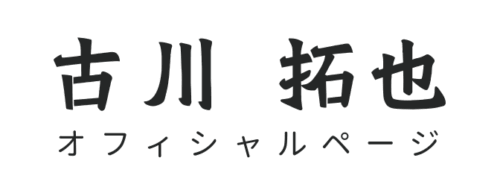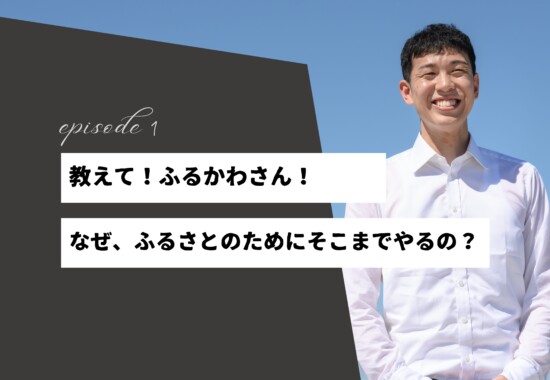~地方と都市をつなぐ新しいカタチ〜
5つの現場で汗をかく実践家・古川拓也氏に聞く
佐世保出身で現在は関東在住。探究教育、地方創生、行政、ビジネス、スポーツの5つの現場で活動する古川拓也さん。自身の様々な経験を活かし、地方と都市部を行き来しながら「みんなの想いを価値ある一歩に変える」インパクト・パートナーとして活動している。 今回は、佐世保市在住でまちづくりや教育に関心を持つ川中が、同世代として、古川さんの等身大の体験談を聞いた。
『故郷のために何かしたい』想いが突き動かした挑戦
古川さんと以前お話をして、印象に残っているのが「若い人たちに、自分が経験したような苦労をして欲しくない」という言葉でした。
実際に地方から東京に上京されて感じた、その「苦労」という部分を具体的に教えてください。
30歳になるぐらいのタイミングで、当時銀行員だった私は、銀行を志望した理由の一つでもある海外勤務という目標を果たした後、次に地方のこと、特に自分の故郷のことを考え始めました。
そんなとき、福岡市の高島市長の本を読んで「若い人でも実は”まち”を動かせるかもしれない」と思ったんです。
でも、そのためにまずは政策のことを理解しなければと思い、明治大学の公共政策大学院に入学しました。そして大学院で勉強しながら、故郷である佐世保市に提案書を持って行こうと考えたんです。
そして実際に、その提案書を持参されたんですよね。
はい。東京には「佐世保市東京事務所」があるので、まずそこに提案書を持って行きました。
東京事務所の方が受け取ってくださって、佐世保の本庁の方にも展開してもらい、いろいろな方とお話しすることができました。
もうそのときは「ふるさと・佐世保のために何かしたい!」
という想いに突き動かされて、突撃するようなかたちで持って行ったので、市役所の方も驚かれたと思います。
いま、立場上、市役所へ持ち込まれる相談を受ける側になっているのでわかりますが、その当時、最初にこの提案書を受けてくれた市役所の方には感謝しかありませんし、きっと日常の業務に追われながら、いろいろと回答をいただいた方には今でも頭が上がりません。
ただ、こうやって広がっていったことは感謝しかないのですが…普通の人は故郷のために何かしたいと思ったとき、東京事務所や市役所には行きませんよね。
本来であれば、そういう人向けのコミュニティや機能がWebサイトだったり実際のコミュニティとしてあって、もっと緩く「こんなアイディアがあるんですけど」とか「今度帰るんだけど、こんな人いませんか」という感じで繋がることができたはずなんです。
確かに、わざわざ提案書を持って行くのは、ハードルが高いですし、誰にでもできることではないですね。
そうなんです。
わざわざ自分のプレゼンテーションを持っていかないじゃないですか。
お付き合いしたい女性に対してもそうですよね。
もっと軽く「お茶でもいかがですか」という感じで。
人間と人間の間ではそういうコミュニケーションが普通なのに、それが簡単にできない。そうするためには、物理的・心理的両方の面で、距離や関係性を再構築しないといけないんです。
これが何よりも私が経験した不自由さで、次の若者にはしてほしくない「苦労」なんです。
地方の若者流出の現実と向き合う
出典:長崎県(https://www.pref.nagasaki.jp/gikai/houkatsu/img06/06-4.pdf)
多くの若者が地元を離れ、都会へ行ってしまいます。
佐世保は全国でも指折りの若者流出のまちです。県全体でも流出が多い。
これにはいろいろな理由があります。仕事がない、学ぶ場所がない。でもないものはないんですから、しょうがないんですよ。そして福岡という快適で物価もそこまで高くない住みやすい場所が近くにある。当たり前の話です。
私自身も実際に関東に住んでいるわけで、ある意味故郷を捨てた人間だと言われれば、それまでです。
でも何か思うところがあると。
出ていく側にしても、これは賛否両論あるかもしれませんが…その人が地元を離れ、大学生や社会人になるまで、元々いた”まち”は数千万円単位でその人にコストをかけてきているんですよね。
教育コストもそうだし、インフラもそう。いろんな面でコストを払っている。
それは自分も以前から感じていました。言い方は悪いですが、地方は都会のための人材をお金をかけて育てているだけじゃないかと…地方が子育てや教育にいくらお金をかけたとしても、育った若者たちは都会へ行ってしまう現状があります。
でも行政はそのコストを払っているということ自体をあまり言わないんです。
なぜかというと、すべての自治体が同じなので、そんなことを言い始めたら公共の役割としてどうなんだという話になる。
でも、何千万というお金をかけてもらっているわけなので、多少は返さなければという想いがあるわけです。
新しい恩返しの形を模索する
返すというと「ふるさと納税」くらいしかパッと思いつきません。
ふるさと納税も返し方のオプションの一つとして、よくできた制度だと思います。
ただ、ショッピング寄りになってきてしまっているし、佐世保から出た人が佐世保市にふるさと納税をするかというと、また別の問題です。
だから、直接的に返してもらうということを行政の立場から言えないのであれば、私のような行政と行政ではない立場がわかる人間が、はっきり言っていかなければいけないんじゃないでしょうか。
若者活躍の取り組みのときにずっと言っているのは「壮大なる種まき」と「愛着を持たせる」ということです。最終的に人間は「この人にやってもらったから、何かお返しをしなければ」という恩返しの気持ちでしか生きていけないと思うんです。そういうものをどれだけデザインできるか、そう思ってくれる若い人をどれだけ増やしていけるかが私の活動です。
愛着とは
自分は佐世保に35年住んでいますが、あまり愛着がなかったんです。たまたま地元で就職できたからそのままずっと暮らしているという感じで…ただ、まちづくりについて考えるようになると、やっぱり自然と愛着っぽいものが出てくるし、ずっとこのまちにいるのなら地元をもっと面白くしたいし、何かやりたいという気持ちも出てきました。
川中さんのように何かやりたい気持ちが湧いたときに、やりたいことが実現できたり、「こんなものがあったらいいのに」という願望が叶うかどうかがすごく重要だと思うんです。
ただ、大人になっていくと、やりたいことが壮大になりがちなんですよね。いろんな経験が増えた分、やりたいことも大きくなる。でも小学生のときは5、6段の跳び箱を跳べただけですごく嬉しかったですよね。大人になって、いきなり15段とか跳べるんじゃないかと思っても、現実的に難しくて諦めたりすることもある。
確かに、まずは小さな成功体験が大切ですね。
若い人たち、特に高校生のときのやりたいことって、まだまだ叶えられる余地が相当にあるんです。小さな願い事を丁寧に100%じゃないけれど、かなりの部分で叶えていくという経験がすごく重要です。
例えば生徒たちから「この場所を自習室のように使いたい」「ここでこんなのをやってみたいから貸してください」と言われたとき、素直に貸して運営させてみる。生徒たちの心に「やれた」という気持ちや達成感が生まれることが大切なんです。
愛着の本質は「人」にある
その一つ一つの「やれた」という体験が「種まき」ですよね。そして、もうひとつは「愛着」が大切だと。
「愛着」というとすごくふわっとしていますが、愛着って考えたとき、最終的には「誰に」というところに寄ってくるんじゃないかと思うんです。愛着は「人」のところに寄ってくるんですよね。
例えばハンバーガー屋さんがあって、初めはハンバーガーが好きだからそのお店に行っていたとしても、通う内にそのお店の誰々さんと親しくなって、だからそこに行きたいという気持ちになる。これが愛着で、つまり人ですよね。
アイドルだってそうじゃないですか。箱推しって言っても、そのグループの中にいる一人一人のメンバーが好きという話なので。
確かに、最終的には人ですね。
もちろん佐世保という空間が好きという人もいるでしょうが、様々な関わりやつながりの中で「私は佐世保のここのこういう人、ここのこういう人が好きだから、佐世保が好き」というふうになっていくはずなんです。それをいかに身近なところでたくさん経験するかが重要です。
愛着というと壮大な概念に陥りがちで、「故郷大好き」「地元LOVE」みたいになってしまう。でも実際はそんな大きいものではなく、最終的には、その人の人生の物語の中で出会った身近な人々なんですよね。
体験から生まれる本当の愛着
ちなみに私の地元は三川内なのですが、中学校には、焼き物を焼く登り窯があって、年に2回、自分たちで作った焼き物を焼くイベントがありました『窯焼成』。当時は夜も生徒が学校に泊まって、火が消えないよう薪をくべ続けるんです。そして、出来た焼き物を三川内陶器市で生徒たちが売るんです。
ふるさと教育で三川内焼きの歴史を教わったり、ろくろ体験をするだけでは愛着はあまり湧かなかったけれど、実際に自分たちで作って売る体験をして、初めて地元の窯元の人たちの気持ちが分かったし、地元の人やお客さんとの交流の中で三川内への愛着が湧きました。
それはすごくいい経験ですね。ポイントは、その身近にあるかどうかということなんです。
佐世保だとハンバーガーや九十九島がありますが、これはどちらかというとコンテンツの話、観光PR的なものです。認知には効くけれど、本質的な意味でのふるさと教育や愛着は、もっとミクロな、身近な話だと思うんです。
私が携わっている福石中学校の魅力発信プロジェクトでも、生徒たちが一番喜んでいたのは、自分たちが作った商品の販売のタイミングで、身近な町内会の人や地域の人に会って、「何でこれやってるの?」と聞いてもらったりする瞬間なんです。”まち”の人との会話で、自分の繋がりがあることを確認できる。身近なところでいかにそういうものがあるかが重要なんです。
福石中学校の魅力発信プロジェクトの様子
観光客の愛着と住民の愛着
国が閣議決定した『地方創生2.0』の基本方針に、実は明確に「ふるさと教育をしなさい」と書いてあります。私が若者活躍の取り組みで4、5年前からずっと言ってきたことが、ようやく同じような目線で取り組める機会が出てきそうで嬉しいです。
一方で、愛着というものを勘違いしないようにしなければなりません。その対象は観光客ではないので。観光客も「佐世保大好き」と言ってくれるかもしれませんが、彼らは帰るわけです。「また今度来ます」という人たちのための愛着じゃない。
もっと身近な愛着が必要ということですね。
そうです。もっとローカルで、もっとミクロな愛着が必要なんです。
おわりに
地方と都市をつなぐ新しいカタチが見えてきた
佐世保出身の古川拓也さんの体験談から見えてきたのは、「故郷を離れる/故郷に残る」という二択ではない、新しい関わり方の可能性だ。
若者たちが地方を出ていく前に、地方でもいろんなことが出来るんだという体験を重ねてもらう。そして、その関わりやつながりの中で、そこに暮らす人に「愛着」を持ってもらう。
ただし、それは地方を出ていく若者たちに、故郷への一方的な愛を強要することではなく、いつでも故郷につながれる、何かやりたいときにアクセスできる、そんな「みなと」を作ること。
そして地方に残る人たちには、そうした若者たちとの新しい関係性を築く機会を提供することなのだろう。
今までは「地方から都市部へ若者が流れていく」という一方通行でしかなかった。でも古川さんのような人が増えることで、これが「循環」に変わっていく可能性がある。
地方の「若者の流出」が「若者の循環」に変わっていく。
そのための様々な取り組みが、いま、佐世保で始まっている!
———古川拓也からのお知らせ———
現在、古川拓也の取り組みに共感し、応援をしたい!というサポーター・寄付を募集しております。ぜひ、ご検討のほどよろしくお願いいたします。寄付ページは以下のバナーをクリックしてご覧ください。