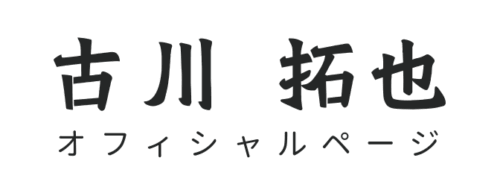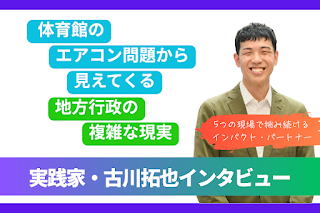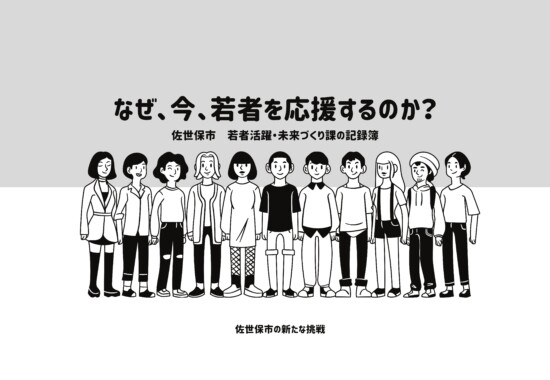大人版・探究で、「問い」を灯せば、人生が動き出す
共感結社モルタル代表理事・古川拓也氏が語る、大人のための探究体験プログラムへの熱い想い
現在、参加者を募集中の「探究実践プログラム」。高校の授業や、大学、社会人の中でも広まりつつある「探究活動」を、今度は大人が体験するという画期的な取り組みだ。なぜ大人が探究を体験する必要があるのか?地域にどんな変化をもたらそうとしているのか?佐世保市在住で、まちづくりに関心を持つ川中が、運営団体「一般社団法人 共感結社モルタル」の代表理事・古川拓也さんにお話を伺った。
5年間の現場経験から見えてきた「決定的な課題」
古川さん、まず「探究実践プログラム」を始めようと思ったきっかけを教えてください。
今回提供を開始する「探究実践プログラム」は、学校の先生や社会人、大学生などを対象にしています。大人向けのプログラムなのですが、実は、ずっとやりたいと思っていたプログラムなんです。
探究という言葉自体は4〜5年前から使われているんですが、主に高校生の「総合的な探究の時間」で使われ始めて、最近は大人の中でも探究活動という言葉の認知度が高まってきています。
私がボランティアから始めた高校の探究支援活動もかれこれ5年以上になります。昔は、教材やテキストもなく試行錯誤でした。

伴走支援をしている様子
5年という長い期間、現場に関わってこられたんですね。
はい。私は、ずっと現場の先生方や地域で伴走支援する人の味方でいることを大切に取り組んできました。でも、どうしても乗り越えられない課題があったんです。それは、「大人の側が、探究する機会が少なすぎる」ということです。
そのため、多くの大人は探究活動を体験する機会がないまま、若者の指導や支援を求められたり、探究的な仕事上のお題に向き合わされているのが現状なんですね。大人の側が、そういうある種のもどかしさを感じながら、高校生や若者、目の前の課題に向き合っていると思うんです。全く経験のない部活・スポーツの指導を任されるような苦しみと同じです。
確かに、自分も「探究」という言葉は聞いたことがありますが、実際にどんなことをするのか漠然としています。
そうなんです。探究の時間って、すごく平たく言うと、いわゆる普通の教科教育とは違っていて、何か答えがあるとかそういうものでもない。一番難しいのは、問いを自分で立てなきゃいけないということです。要するに「何を解きたいのか」ということを自分で設定しなきゃいけない。
みんなこの探究活動を、例えば高校生に指導するとか、地域で若い人と伴走しようとする場合、どうしても社会人自身がやったことがなくて経験がなくて、もうどうやったらいいかわからないっていうのが、実情としてあるんです。
世代間ギャップを埋める、実践的な学びの場
大人が探究を学ぶ必要性について、さらにもう少し詳しく教えていただけますか。
今の社会人って、学校教育の中で探究的な学習を受けたことがないんです。私もそうなんですが、全然受けたことがなくて。でも今、会社で「自分の会社の分析をしてくれ」とか「この商品をもっと売るためにはどうすればいいか、課題を分析しろ」とか、そういうことをいろいろ言われると思うんですよね。
実際、具体的にどうすればいいのかわからないし、もっと言うと、今の若い世代っていうのは「自分自身と深く向き合いなさい」っていうふうに自己分析をかなりさせられている。僕らの世代って自己分析といえば就職活動の時にちらっとやったかなぐらいなんですが、どこまで深く自分を知れているかっていうのもよくわからない。
確かに、今の若い人たちと私たちの世代では、受けてきた教育が違いますね。
そうなんです。「若い人を応援したいんだけど、若い人ってどんなことを考えているのかわからない」というようないろんなモヤモヤを抱えながら、学校の先生、あるいは社会人の立場、NPOの立場、大学生の立場で悩んでいる。これを解決したいというのが今回のプログラムの大きな考え方になります。

自己探究のワークの一例・興味関心を深掘りしていく
「問い → 行動 → 仲間づくり」を8ヶ月で一気に体感
具体的にはどのような内容になるのでしょうか?
コンセプトは、「問い」を灯せば、人生が動き出す、です。自己探究のSTEP1、伴走実践のSTEP2、企画運営のSTEP3の3つのステップを用意していて、まずは、8ヶ月で行う「問い → 行動 → 仲間づくり」を一気に体感するSTEP1の募集を開始します。

STEP1は8月から来年3月まで続く8ヶ月間のプログラムです。詳しくは公式ホームページをご確認いただければと思いますが、自分の軸を可視化して実際にアクションに繋がるような自己分析を体感していただいたり、実際にまちづくりを実践されている生の現場を見られるフィールドワーク、AI活用演習など、内容はかなり充実していると思います!

STEP1の概要
3つのステップで構成される包括的なプログラム
残りのSTEP2とSTEP3についてもお話してもらえますか。
はい。ステップ2の伴走実践では、今度は応援する側として、学生さんのアクションを支援する段階です。実際の高校生を題材にして、その子たちがやりたいことを聞きながら、地域のリソースや行政と連携してプロジェクトを形にしていきます。
例えば、高校横断型コミュニティSaseboChangeを伴走いただいたりすることを考えていますが、松浦鉄道を貸切ってイベントをやりたいという場合、松浦鉄道さんと話をしなきゃいけないし、なぜやるのか目的を一緒に考えなきゃいけない。チラシやPOPをどうやって作るのか、運賃をどうやって集めるのかなど、いろんなことを一緒に考える実際の伴走経験を通じて、相手方の思いを形にするという部分を体験してもらいます。

ステップ3は企画運営。おおむね2年目3年目の話になりますが、1期生の皆さんの中から、このコミュニティをもう少し運営したいとか、プログラムの設計をもっとアップデートしたいという方に、そういった活動をやっていただくステップです。
参加の仕方に柔軟性はありますか?
ステップ1は参加必須ですが、ステップ2と3については、ステップ1が終わったタイミングでご希望に沿いながらやっていくこともあります。「もっと先に進みたい」という方がいれば、そこは柔軟に対応していきたいと思っています。
できればこの1→2→3というプロセスは踏んでいただくと、実際にフルパッケージで身に付くということなので、ご検討いただければと思います。
佐世保市との連携が生む、実践的なプログラム
プログラムの特徴や強みについて教えてください。
強みとしては、佐世保市との強固な連携です。私自身が仕掛け人として立ち上げに関わった佐世保市の若者活躍・未来づくり課としっかり連携しています。プログラムの中にも市役所との連携施策が多いですし、地域連携みたいなことを元々強く打ち出しているので、皆さんが単に学んで終わりではなくて、ちゃんとアクションができるように伴走ができると思っています。
加えて、 共感結社モルタルは、これまで学校や地域の若い人たちの伴走をしてきました。長崎県内の高校の伴走支援実績も相当に多いと思っています。
数年間の間に私たちが蓄積した内容をベースにやっていくので、何か机上の空論的なものではなくて、しっかり身になるものをベースにプログラムを展開していきます。
これまで「こうやったらいいですよ」っていうアイデアはすごくたくさん提供してきていて、僕たちも直接向き合っているんですが、やっぱり自分がやること、やってみて体感したこと以上のものはないんですよね。自分がやったことがあって経験があって、それを教えられるっていうのが実は一番早くて、そういう実践を通じて経験してもらうのが一番だという信念のもと、今回このプログラムを作っています。
参加しやすい仕組みづくり
参加を検討している方にとって、どのような点で参加しやすいプログラムなのでしょうか?
ご自宅や職場から参加が難しい方向けの集まれるリアルの場とオンラインのハイブリッド開催で、主に夜間中心となりますので、仕事や授業の後でも参加できます。
また、全セッション録画対応なので、参加できない日があってもキャッチアップが可能です。チャットツールで相談できたり、最大限フォローさせていただきます。(※講師はオンライン・リアルのどちらかの会場からになります)
また本プログラムは、三菱みらい育成財団の助成を受けて実施するため、参加費は無料です。交通費や通信費などは自己負担になりますが、プログラム自体に参加することには特に費用がかかりませんので、ご安心ください。
無料というのは参加しやすいですね。ぜひ色々な大人の人に参加してもらいたいです。
今回は学校の先生だけが対象ではなくて、いわゆる地域の普通に働いていらっしゃる会社員の方や、公務員の方、大学生、NPOの方、そういった方も対象になっています。
多様な職種の方が参加されることで、どのような効果が期待できるでしょうか?
それぞれ違う立場の方が集まることで、様々な視点での学びや気づきが生まれると思っています。高校の先生だけでなく、地域で活動している方々も一緒に参加することで、より実践的で多角的な視点での探究体験ができるんじゃないかと考えています。
高校生コミュニティとの連携で見える未来
実際に高校生との関わりもあるんですね。
はい。7月21日に「Sasebo Change ファンミーティング」を開催します。これは、ステップ2で伴走予定の高校生コミュニティSasebo Changeの活動報告会です。実際に地域で活動する高校生の姿を見ることができます。
彼らがどんなことを考え、どんな挑戦をしているのかを知ることで、参加者の皆さんも「自分にもできることがある」と感じてもらえるはずです。
「地域の未来を一緒につくる仲間」への熱いメッセージ
最後に、参加を迷っている方にメッセージをお願いします。
この「探究実践プログラム」は、決して「皆さんが何もできていないから学びに来てください」という上から目線のものではありません。
そして、無理やり何かを強制するものでもありません。
それぞれの得意分野や興味・関心を出発点に「私ならここはいけるぞ」という一歩を見つけてもらうための探究実践プログラムです。
AIがこれほどまでに進化した今、私たちにしか生み出せないのは『実体』だと思っています。
何かをやってみたことで、社会が少し変わった。
誰かが喜んだ、悔しがった、挑戦してみたら意外にも若い人が大きなことを成し遂げた——
そんな、リアルで、エモーショナルで、熱を帯びた“実体”こそが、これからの時代に価値を持つと考えています。
このプログラムで得られた経験は一生モノになるはずです。あなたの「もやもや」を”行動”へと変えるその第一歩として、ぜひ『探究実践プログラム』に参加してみてください。ここには、地域の未来を一緒につくっていく仲間がいます!
おわりに
現代社会において、「探究」という言葉は徐々に浸透してきているものの、多くの大人にとってはまだ馴染みのない概念かもしれない。しかし、古川さんの話を聞いていると、探究とは決して特別なものではなく、私たちが日常的に直面する課題や疑問に対して、自分なりの問いを立て、行動を起こし、仲間とともに解決策を見つけていく、極めて実践的なプロセスであることがわかる。
特に印象深いのは、「大人の側が探究する機会が少なすぎる」という指摘だ。確かに現在の社会人世代は、答えのある問題を効率的に解く教育を受けてきた。しかし、変化の激しい現代社会では、正解のない問いに向き合い、自分なりの答えを見つけ出す力がより重要になってきている。
また、この取り組みが単なる学習プログラムにとどまらず、佐世保市との連携により実際の地域課題解決に繋がっていることも注目すべき点だ。学んだことを即座に実践に移し、地域の未来を共に創っていくという循環が生まれている。
古川さんの「リアルで、エモーショナルで、熱を帯びた”実体”こそが、これからの時代に価値を持つ」という言葉は、AI時代を生きる私たちにとって重要な示唆を与えてくれる。技術がどれほど発達しても、人間が実際に行動し、感情を込めて取り組む「実態」に勝るものはないだろう。
佐世保市で始まったこの取り組みが、やがて他の地域にも広がり、日本全体の地域づくりに新たな可能性をもたらすことを期待したい。そして何より、一人ひとりが自分の「問い」を見つけ、行動を起こし、仲間とともに歩んでいく。そんな社会が実現していくことを願っている。
———古川拓也からのお知らせ———
現在、古川拓也の取り組みに共感し、応援をしたい!というサポーター・寄付を募集しております。ぜひ、ご検討のほどよろしくお願いいたします。寄付ページは以下のバナーをクリックしてご覧ください。